
DIARY
2025年8月
8月15日 嘘と真実の間に咲く花火 -疑う眼と信じる恋のおはなし-
■
SNSにすごいポストが流れてきた。オレンジ色の政党の支持者だった。
「どうやら地球は平面らしいのです。よく考えてみたら、地球が丸くて高速で回転していたら、私たちは弾き飛ばされてしまいます。なんでそんなことに気がつかなかったのか、常識を疑ってみることは大切ですね」
僕はそれを読んで頭がクラクラすると同時に、ほろ苦い出来事を思い出していた。

■
50代、無職。重度の精神疾患。プロフィール欄にそう書かれていたら、マッチングアプリでの出会いはほぼゼロだ。アプリに限らない。現実の世界でも僕を恋愛対象として見る人などいない。それが長年の経験則だった。
この国では僕の存在そのものが「冗談」か「不安材料」として扱われる。家族・親族の中でも、友人・知人の中でも、僕の病気はいつも偏見と差別の対象だった。罵倒や冷たい沈黙を受け取る年月が過ぎて、「理解されない」という感覚は呼吸みたいに当たり前になってた。
■
それでも人恋しさは消えなかった。恋愛であれ友情であれ、自分を丸ごと受け入れてくれる人と出会いたいという願いは捨てられなかった。それは宝くじの1等よりも低い確率の夢で、期待したら傷つくだけだと諦めてもいた。
そんな中で、マッチングアプリの画面に彼女の写真が現れた。20代前半。柔らかい笑顔と芯の通った瞳。プロフィールには短く誠実な言葉が並んでいた。あまりにも現実離れした存在感に、「自分とは別世界の人」だとすぐに思った。普通なら右スワイプして二度と画面に出てこない。けどそのときはなぜか指が止まり、軽い気持ちで「いいね」を送った。それが「奇跡」の入口になるとは、その時は思ってなかった。

■
最初のデートは少し背伸びをした。都心の落ち着いた雰囲気のレストラン。白いクロスのかかったテーブル、低く流れるジャズ。彼女は写真よりもずっと美しかった。派手さではなく内側から滲み出るような穏やかさと芯の強さが、最初の一瞬で伝わってきた。彼女は大手ミスコンのファイナリストだった。受賞は叶わなかったけど、それはどうでもよかった。目の前の彼女は、コンテストという舞台から離れても人を惹きつける雰囲気を持っていた。
席につくと、彼女はにこやかにこう言った。「ちょっと緊張してます」。「僕もです」と笑い返すと、その緊張はすぐにほどけた。おしゃべりの波長が不思議なほど合った。会話は軽やかに、だけど薄っぺらくはない。冗談を交わし、笑い、時には誠実に自分の思いを語った。そのバランスは、長い友人みたいだった。
■
芸術の話もした。彼女は美術館巡りが好きで、最近見た展覧会の印象を楽しそうに語った。「作品の背景まで知ると、全然見え方が変わりますよね」。
瞳は知性と好奇心で輝いていた。音楽や映画の話にも自然に広がり、互いの趣味の地平が少しずつ重なっていくのを感じた。
時間はあっという間に過ぎ、別れ際には「また会いましょう」と自然に言葉が出た。社交辞令ではない。次に会うのが楽しみな気持ちが互いの笑顔に滲んでいた。

■
二度目のデートはぐっとカジュアルに。生牡蠣が評判の居酒屋を彼女が提案してくれた。暖簾をくぐると磯の香りがふわりと漂い、活気のある店内に案内された。牡蠣は海そのものを閉じ込めたような輝きをしていた。レモンを絞って頬張ると、海水の塩気とクリーミーな甘みが口いっぱいに広がる。「美味しい!」と顔を見合わせて笑い合った瞬間、互いの距離は一層近づいていた。
お酒も二人の波長を合わせてくれた。彼女は安いお酒が大好きで、大きなジョッキをどんどん開けた。僕も負けじとスルスル飲んだ。酔いは浅くて心の緊張をほぐす程度、会話は尽きなかった。
■
店を出ると夜風が心地よかった。街灯の下で彼女は少し笑いながら「楽しかったです。また行きましょう」と言った。その声に含まれた温度は、最初の出会いの時よりも確かに温かく柔らかかった。あの夜僕は初めて思った。この人となら年齢や病気を超えて、「ひとりの人間」として向き合えるかもしれない。
二度のデートは短くも濃い時間だった。彼女の笑い方、話のテンポ、酒を飲むときの嬉しそうな仕草。どれも僕に「こんな人と一緒にいたい」という感覚を芽生えさせた。それは長く封じ込めてきた自尊心を、そっと呼び起こすような体験だった。

■
でもその幸福感の影に、微かなざわめきが忍び寄っていた。きっかけは彼女のSNSだった。ある日タイムラインに奇妙な動画が流れてきたのだ。小さな金属の粉がうごめき形を変えていく。コメント欄には「これがコロナワクチンに入っている金属チップ」「人類を支配する計画」といった文字が並んでいた。
最初はピンと来なかった。ただの理科実験かアート作品か...そう思いたかった。たぶん油でまとめた砂鉄を、下から磁石で動かしているのだろう。映像自体は単純な仕掛けだけど、それを「証拠」として拡散している彼女の意図は、簡単には理解できなかった。
■
その後も彼女の投稿には反ワクチン的な言葉やリンクが増えていった。「体内に金属が…」「マイクロチップが…」文章は真剣で疑いを差し挟む余地を与えなかった。二度目のデートのときに見せてくれた穏やかな笑顔、その同じ人が書いているとは思いたくなかった。
もちろん人は多面的だ。政治や科学に対する意見が異なっても、関係を続けられる場合もある。だけど陰謀論は事実認識そのものを揺さぶる。「地球は平らだ」と信じる人と「地球は球体だ」と信じる人が、風景について語り合えるだろうか。

■
僕は葛藤した。彼女の優しさや知性を信じたい気持ちと、目の前で広がる世界観の溝。「これは一時的な興味だろう」と自分に言い聞かせても、SNSはそれを否定するように、確信めいた色を濃くしていった。
二度のデートの余韻は確かに残っていた。でもその余韻の中に、ほのかな苦味が混ざり始めた。もしかしたらこの先、僕たちは同じ景色を見られなくなるかも知れない。そんな予感が心の奥で芽を出していた。彼女のSNSに陰謀論的な投稿が増えるたび、僕は心は揺れた。「人は自由に意見を持っていい」と思う一方で、どうしても譲れない領域があった。
■
僕は彼女と出会う少し前、新型コロナ感染症に罹患していた。持病があったことに加えて、感染の波は東京オリンピックの時期と重なっていた。医療現場は逼迫し、機器が徴収されて、僕のための人工呼吸器はなかった。そのまま3週間にわたって生死の境を漂うことになった。
酸素を求めて必死に呼吸する感覚は今も忘れられない。意識が途切れがちになる中で、看護師が何度も名を呼んで、数字と数値を確認する声が聞こえていた。一歩間違えば、僕はあのまま帰ってこられなかっただろう。

■
それでも僕は科学的な医学によって救われた。的確な診断、酸素投与、薬の調整、感染症対策...それらすべてが、最終的に僕を生かした。だからこそ、ワクチンを含む公衆衛生の努力が、いかに多くの命を守っているかも実感として知っている。
そんな僕にとって、「ワクチンは人類を支配するための毒」という戯言は、単なる意見の違いではなかった。それは命を救ってくれた現場と人々を全否定する言葉に聞こえた。僕を生かした科学と医療への侮辱にさえ感じられた。
■
彼女に直接問いただそうかとも思った。でもその会話がどういう結末をもたらすかは想像がついた。彼女はおそらく自分の信じる情報源を根拠に挙げて、僕の言葉を「洗脳された意見」として退けるだろう。陰謀論は一度信じ込むと、反証を逆に「陰謀の証拠」として取り込む性質がある。彼女がそうなる可能性は充分にあった。僕は迷った。波長が合って心を許せる貴重な存在。でもその土台に深い亀裂が入りつつある。このまま見なかったことにして会い続けるべきか、それとも...。
答えは時間が経つほどに明らかになっていった。SNSの投稿はますます過激になり、医療や科学そのものを否定する調子が強まった。僕の中で病室と酸素マスクの感触がよみがえるたび、彼女との距離は遠ざかっていった。

■
別れの直接の理由は、ワクチンでも陰謀論でもなかった。体感気温だった。暑い夏、冷房の効いた部屋で「寒い」と感じる女性は珍しくない。彼女はSNSでそのことを繰り返し投稿し続けていた。「今日も冷房が寒い」「電車の冷房がきつい」。それが僕の中で少しずつ冷めていく原因になった。
ある日つい口にしてしまった。「そんなに何度も書かなくていいんじゃない?」。それは些細な指摘のつもりだったけど、彼女ははっきりと憤慨した。温度の感じ方は人それぞれ。彼女にとっては大切な感覚を軽んじられた瞬間だったのかも知れない。
■
その張り詰めた空気に、僕はもうひとつの不満を滑り込ませてしまった。「あなたが信じている反ワクチンの陰謀論にも、納得できない」。言ってしまった瞬間、もう関係は元には戻らないと悟った。
彼女は落ち着いた言葉で答えた。「ワクチン接種は自由意志です」。確かにその言葉自体に間違いはない。当時の社会は「みんなで打って感染を抑えよう」という空気が強かったけど、法的には接種は義務ではない。でも私にとってその言葉は、あの日の病室や酸素マスクの感触を無かったことにするように響いた。彼女は自分の信念を曲げる気はないようだったし、僕も自分の体験と信頼を裏切ることはできなかった。それからお互いに連絡を取ることはなかった。

■
別れの引き金は、冷房の温度というあまりにも小さなことだった。だけどその背後には、温度以上に埋められない価値観の差が横たわっていた。僕の中では、また理解者を失った事実の重みが沈んでいった。彼女はこの国で数少ない、僕を丸ごと受け入れてくれた人だった。
50代、無職、重度の精神疾患...そんな条件の僕を、恋愛対象として見てくれる人はほとんどいない。だからこそ関係が壊れたときの喪失感は、恋愛の終わり以上の意味を持っていた。再び手に入る可能性が限りなく低い「奇跡」を失った感覚。
■
夏の終わりに街を歩くと、冷房の効いた店の外に出た瞬間の温かい空気が頬をなでた。あのとき彼女が「寒い」と言った気持ちも、今なら少しはわかる気がする。だけどももうその思いを伝える相手はいない。
彼女と連絡を絶ってから、何度も思い返した。笑い合った瞬間、芸術の話で目を輝かせた表情。陰謀論も体感気温の違いも別れの理由ではあったけれど、同時にそれらは彼女が持つ無数の側面の一部にすぎなかった。
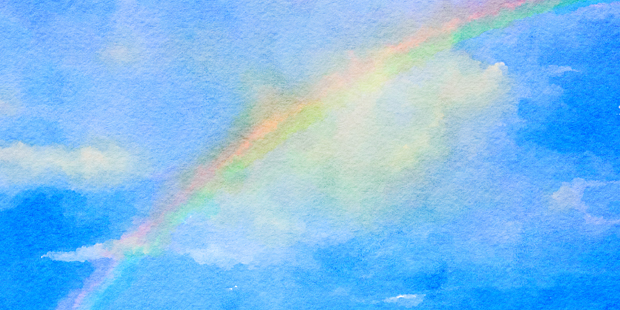
■
関係が終わった今も、「あれは夢だったのではないか」と思うことがある。50代、無職、重度の精神疾患...そんな条件を知った上で、恋愛対象として私僕を見てくれる人なんて普通なら現れない。でも現れた。ほんの短い時間だったけど、確かに出会い、笑い、理解され、受け入れられた。
この事実は僕はにとって大きな意味を持つ。それは「不可能ではない」という証拠だからだ。社会の常識や確率論がどうあれ、奇跡は一度起こった。ならば、もう一度起こる可能性だってゼロではない。もちろん二度と同じ人には出会えない。彼女は彼女で代わりはいない。でも僕がもう一度誰かを受け入れ、誰かに受け入れられる可能性は、まだこの世界のどこかに残っているはずだ。
■
だから僕は、この出来事を封印しないことにした。悲しい記憶としてでなく、再び人とつながるための羅針盤として残しておく。たとえそれが宝くじみたいな確率でも、当たりを引いた経験があるのとないのとでは心の構えが違う。
この文章を読んでくれた誰かが、もし僕と同じように「理解されること」を諦めかけているなら、伝えたい。奇跡は必ずしも長く続くとは限らない。だけど一瞬でも起これば、それは一生の意味を持ちうる。そして一度あったことは、二度目がまったく不可能とは限らない。僕はまだ、もう一度を信じている。
|