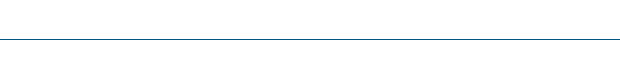
DIARY
2001年冬
12月1日 All Things Must Pass

■
雅子様出産の1/100も話題になりませんでしたが、George Harrisonという素晴らしいミュージシャンが亡くなりました。58歳。
テレビはJohn Lennonの演奏シーンを写し、Paul McCartneyの曲を流し、Ringo Starrのソロライブの模様を放映して彼の死を報じました。間違われ方まで彼らしい。生き方も死に様も華々しかったJohn、器用に世渡りするPaul、誰からも愛されたRingoと比べて、彼はいつも3歩下がって苦悩していました。
■
僕が彼の存在を強く意識したのは、1996年にリリースされたThe Beatlesの「ANTHOLOGY 3」というレアコレクションアルバム。このCDには、なかなか自分の作品を取りあげてもらえないGeorgeがひとりで製作したデモテープが収録されていました。彼のもどかしい気持ちが、僕のやるせない胸の内にストレートに突き刺さってきた。それからレコード屋をまわる度に、Georgeのアルバムを探しました。
■
彼はいつも立ち位置に迷い、自分と現実世界をつないでくれるパートナーを探し続けてきたと思う。そんな58年が終わって、音楽だけが残った。いい人生だったんじゃないかな。歌います。
C My sweet Gm Lord, C mm my Gm Lord, C mm my Gm Lord
I really want to F see you, Dm really want to F be with you Dm
Really want to F see you, my Lord, D7 but it takes so long my Gm Lord
このあと転調するけどそんなに難しくないので、楽器をお持ちの方はご一緒に。
 ■
こんな無名サイトで彼の冥福を祈ったところで届くはずもないので、彼の音楽が聴けるアルバムを何枚か紹介したいと思います。よかったら探して聴いてみてね。君の耳でね。
The Beatles / Anthology 3 (1996)
All Things Must Pass (1970)
The Concert For Bangla Desh (1972)
George Harrison (1979)
Best Of Dark Horse (1989)
Portrait Of A Legend (2002年リリース予定)
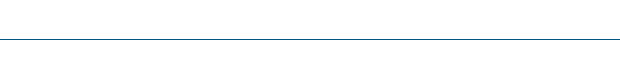
12月4日 ネズミ撲滅
■
11月19日の日記に、マウスは体に悪いって話を書いたところ、思いのほかたくさんのリアクションを頂きました。マウスでデザインの仕事をしている人は得てして背骨が曲がっているようです。整体に行ってみたい。たぶんボキっの元がいっぱいたまってると思うんだ。パソコンの中身が画期的に進化してるそばで、入力デバイスだけが大昔のままなのは大きな問題です。

■
僕はむかし某有名パソコンメーカーに勤めてたことがあるんですが、メーカーの人間はパソコンが大好きでしょうがないので、多少の不便さには気づかないんです。そもそも彼らは机の上がとても汚くて、モニターの両側に周辺機器だの雑誌だのを山積みにした上にマウスを乗っけて、ハンドルを改造した暴走族みたいな格好で仕事をしてるの。あれで肩がこらないのか不思議に思うんだけどやっぱりこってるらしい。
■
最近、我が家の電化製品が続々と買い替えの時期を迎えています。新しいのはどれも画期的に便利になってる。こないだ買った冷蔵庫は、なんと内壁に霜がつきません。驚いた。あとドアの小棚がジャストサイズなの。マヨネーズを立てて保存する時代は終わった。使ってみればわかる。目が覚めるから。冷蔵庫ビバ!
パソコンも、スピードや容量の勝負は休戦にして、こういう方面で凌ぎを削ってほしいものです。ラックからOSレベルまでトータルで使い勝手を見直す時期にきていると思う。これは人類の課題として。
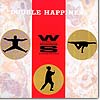
■
最近入手したアルバムです。World Standard / DOUBLE HAPPINESS 鈴木惣一朗さんのポップでダンサンブルな一面。こういうことも出来ちゃうのね。あがた森魚 / 佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど 極私的な想い出を語るこじんまりとした佳作。「普遍」って案外こんなところに潜んでるのかも。Todd Rundgren / A Cappella Tour 85年のライブ。サンプラーを駆使した同名アルバムとはうってかわってゴスペルな出来。World's End Girlfriend / farewell kingdom Mike Oldfieldの空きトラックにOvalがいたずらしたような一枚。Paul McCartney / DRIVING RAIN 曲のクオリティにムラが...。アルバムとしては辛い。
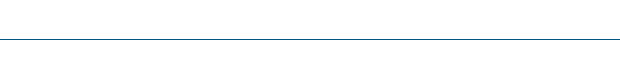
12月11日 驚きと感謝をこめて
■
ちまたで面白いと評判の菊地成孔さんの日記を読みました。うーん面白い。毎日書いてるのに面白い。毎日間違いなく面白い。宇多田ヒカルさんの日記と双璧です。持って生まれた体力と獲得してきた洞察力。一語一語がテンション高くてたぶん勢いで書いてるんだけど、句読点の絶妙な置き様はやっぱりミュージシャンです。グルーヴ!

■
僕の日記も今よりは面白かった時期がある。あの頃は読者の方からメール貰っちゃうと何度も読み返してニヤニヤしたり、次回の日記はあなたに捧げますみたいな。今は「そういや更新してないからなんか書くか」と。菊地成孔さんの言葉を借りれは「恋が足りない」。人に媚びた文章を書くつもりはないけど、もう少し感謝しながら生きたほうがいいと思った。
■
最近はウクレレ教室に通ってます。僕のウクレレは先生方に大変誉められる。腕じゃなくて楽器が。軽い西村雅彦状態。これを売ってくれたイシバシ楽器の店員さんは値段のつけ方を間違えたのではないか。
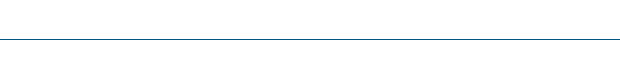
12月17日 猫の寝言
■
風邪ひいてますげほげほ。インフルエンザブームには2週間ほど乗り遅れてるそうですが。竹内結子さんがルルを持ってお見舞いに来てくれたら「大丈夫だよ」と答えたい。そんな妄想にかられつつひとりシーツにくるまる日々です。
世の中は年末に向けて面白いイベントがめじろ押しだったようで、うーん残念。見たかったライブも何本かあったんだけど。そんなわけでこれといって話題もないんでたまには猫の話でも書く。

■
僕は基本的に、猫に赤ちゃん言葉で話しかける人間は信用しません。そんなのただのポーズでしょう。「わたしは猫を可愛がる善良な小市民ですよ」っていう。
赤ちゃん言葉っていうのは、親子の絆の中から必然的に生まれてきた喋り方です。認知科学的にみても、赤ちゃんの可聴域に合わせて喋ろうとすると、自然と赤ちゃん言葉になるんだそうです。猫に赤ちゃん言葉で話しかける根拠なんてどこにもない。というわけで、僕は猫とも普通に話します。「布団に入りたいのか出たいのかはっきりしろ」とかね。大意は伝わります。

■
赤ちゃん言葉は使わないけど猫言葉はよく使う。和猫なら、「にゃあ」と一声かければこちらの気持ちは通じます (洋猫には通じない。英語やペルシャ語で「にゃあ」と言えばいいんだろうか) 。ただしこちらから一方的に話しかけるのみで、ヒアリングは無理。猫の言わんとしていることはたぶん一生わからないと思う。そもそも彼らは僕のことをどう思ってるんだろう。自分より10倍もでかい生き物に食事をねだるやつの気持ちなんてわかるはずがありません。例えば君、象にご飯を貰ったり同じシーツにくるまる生活なんて想像できるかい?
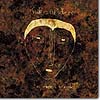
■
最近お気に入りのアルバム。Moonriders / dire morons TRIBUNE やったあ、お帰りなさいMoonriders。ラフで抽象的で、初心者にはお薦めしないが僕は聴く。Jools Holland / Small World Big Band George Harrisonのラストレコーディング。腕利きのブルースピアニストが豪華ゲストを招いて最後の晩餐。They Might Be Giants / MINK CAR 研究室ロックのパイオニア。久しぶりのアルバムでも全然枯れてない。Roger Nichols and Paul Williams / We've Only Just Begun ソングライターチームとして大成功する前のデモテープ集。Kirinji / Fine アルバムを出す度に日本のポップス史を集大成するキリンジ。またしても最高傑作。
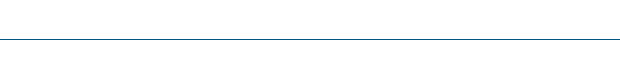
12月24日 とある月曜日
■
風邪、治りました。それだけ書きたくて更新したんですが。お見舞いのメールが続々届いてるんで申し訳ないやらこそばゆいやら。オフネットでは地味に慎ましく生きてるんで、構ってもらうことに慣れてないんだよ。

■
さて、今日がただの平凡な月曜日なのは言うまでもありませんが、寂しんぼうの君や僕にとっては年に一度のお楽しみ、「明石家サンタ」の放送日でもあります。この番組が近づいてくると、そろそろ今年もまとめに入らねばという気がしてきますね。
今年はミュージックフリークとして新しい発見の多い年でした。エレクトロニカ、ラヴ! アメリカンルーツものも面白かったし。シンプルな好盤が多かったな。年末恒例のサンプラーCD作りにも力が入るというものです。欲しい、という奇特な方がいらしたら差し上げます。ただし君の作ったセレクションと交換でね。カセット、MD、CD、LP、MP3いずれも可。それでいいならメールください。
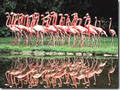
■
きのうテーマパーク系のサイトをまわっていたら、行川 (なめかわ) アイランドの遺物に遭遇してしまった。ああ行川アイランド。昭和50年代を生きた東京の子供たちにとっては憧れのパラダイスでした。
南総の断崖を切り開いた広大な敷地に並ぶコテージ、そして動物たち。目玉はフラミンゴショーで、飼育係に追い立てられたフラミンゴが水際をばしゃばしゃ逃げまどう姿がダンスしているように見えなくもない、という代物だった。

■
それと人気を二分していたのが孔雀の飛行ショー。スターウォーズのテーマ (ディスコバージョン) にのせて、丘の上から孔雀が滑空してくるのです。丘の上をよく見ると、飼育係が孔雀を放り投げているのがわかる。しかもときどきホロホロ鳥が交じってる。拡声機から流れる歪んだディスコミュージックと、ホロッホーいいながら歩き回るホロホロ鳥、そして遠くに響く潮騒の音をまだ覚えています。
しかし千葉方面のテーマパークといえばネズミーランドにその地位を奪われ、さらにネズミーシー開園に併せて行川アイランドはその使命を終えたみたいです。そういえばマザー牧場はまだあるのかな。調べてみよう。
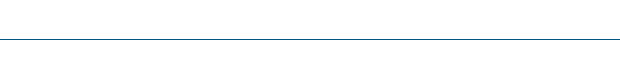
12月26日 死ぬかと思った

■
イヴの夜にサンタさんが来てADSLセットを届けてくれました。So-netも粋なことしてくれる。喜び勇んでセッティングを始めたら、突如前代未聞の腹痛が勃発して七転八倒。それから6時間の間に体重が4キロ落ちた。括約筋の活躍でなんとかコントロールできたけど。
この悲惨な状況を「明石家サンタ」に伝えようか救命救急センターに伝えようかしばし悩みましたが、結局どちらにも電話しませんでした。
■
翌朝になっても動けず、am / pmの宅配サービスを頼もうと思って最寄りのお店に電話。散々たらい回しにされた挙げ句、我が家がサービスエリア外であることが判明しました。最後の頼みで母親にS.O.S.を発信。ポカリスウェットとウィダーインゼリーと猫のエサを所望したにもかかわらず、彼女は手作りドリアと植木鉢とお金を持って現れました。母親って得てしてそんなものです。
一昼夜が過ぎて、今はようやく水分が取れるようになったところ。死ぬかと思った。まじで。
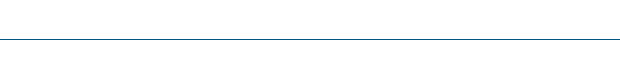
1月1日 歴史の中の明日

■
あけましておめでとうございます。ほんとはなにがめでたいのかよくわかんないんですが。今年ほど年越し感に欠ける年越しはないね。1999年・2000年・2001年と文字面的にかっこいい年が続いた後で、2002年っていわれても盛り上がりようがない。
自分の歩みをしみじみと振り返るには、1年という期間は短すぎると思いませんか。加速を続ける社会に対して地球の公転速度は変わらないから、相対的に1年が早く感じるんです。人間の生活リズムが、地球に生きる生物としてのサイクルからずれてしまったような気がする。そして何もかもが時間に葬り去られて、明日が無理矢理やってくる。
■
とりあえずミュージックフリークの伝統行事といたしまして、2001年によく聴いたレコードをここに並べて讃えたいと思います。2001年は、ポピュラーミュージックの歴史に思いをはせながら、その延長線上に今の音楽があるってことが少し見えてきた。そういう大きな流れの中で、世代交代がじわじわと進んでいることもわかった。クールな音とあったかい音、オーガニックとエレクトロニック、20世紀の二項対立が溶け合って新しいことが起きそうな予感がしています。

red curb Rei Harakami
until tomorrow Manual
Angel In The Dark Laura Nyro

新人賞:Matthew Jay
ベストライブ:Patti Smith
ベストサイト:菊地成孔
君に胸キュン:小林史枝 (Ya-To-Iサポート)
■
ええと、それからデザインをリニューアルしました。前のはInternet Explorerで見ると日付がはみだしちゃったりでなにかと都合が悪かったの。今回は極力シンプルな感じで。当初の目論みとはだいぶ違うんだけど、とりあえず様子を見ます。使いにくいところとかあったらどんどん教えてね。
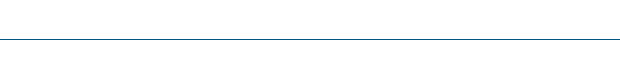
1月7日 愛しのロージー

■
日本のポップ史に燦然と輝く名曲、松尾清憲さんの「愛しのロージー」。若者はベスト盤を買って聴け。
ウクレレという楽器はダウンストロークとアップストロークの感じを近づけるために、1弦と4弦が高い独特のチューニングをします。でもこれじゃ音域が狭いので、1弦を1オクターブ下げて低音を確保することがある。これをローGチューニングと言います。ウクレレ教室の先生がローGにしてるんで、僕も真似して張り替えてみた。ちょっとギターっぽい音になっちゃうんだよな。本当はスタンダードとローGの2本欲しいところです。

■
最近はそんなこんなで思いついたことを即実行、我ながらわりと行動力がある。ウクレレに続く習い事シリーズ第2弾として、英会話教室に通うことにしました。ああ英会話。それは我が人生の根幹に関わる一大テーマです。英語を得意げに話す人ってちゃらちゃらして大嫌いだったの。かといって日本が大好きというわけでもなく、中途半端な国の中途半端な若者として、逃れ逃れて生きてきたわけですが、自分のアイデンティティを確認する意味でも英語はやらないと、とふと思った。ハローハロー。山下さんの実力だと下から2番目のクラスですって。お母さんごめんなさい。勉強してるふりしていっつも漫画を読んでたのです。
■
連絡事項。予告したとおり、去年のお気に入りナンバーを集めたコンピレーションを作りました。欲しい、とかいう珍しい人はメールください。君のお手製コンピとトレードしたい。
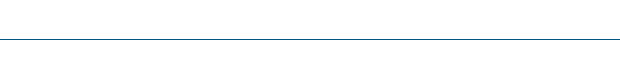
1月13日 マック人生

■
MACLIFE誌廃刊。マッキントッシュ文化の衰退もついにここまで来たかって感じです。実は僕、MACLIFE編集部でバイトしてたことがあるんです。雑誌の編集っていうと平均睡眠時間3時間みたいな世界を想像しがちですが、MACLIFEはのんきな職場でした。たかがバイト君の分際で編集後記を書かせてもらったり、送別会では生まれて初めてキャビアというものを食べた。
■
当時のパソコンはまだまだエンジニアのための道具で、一般人にはとても遠い存在でした。でもマックは開発者もヒッピー上がりだし、フレンドリーで柔軟で「僕らの道具」って感じがした。編集部には、イラストレイターやら売れないミュージシャンやら食えないダンサーやら、パソコンとは縁のなさそうな人達が出入りしてみんな夢を見ていました。僕はいまでもマックに夢を見ている。実状は灰色のウィンドウズに駆逐されているとしても。だからお願いだー。ウィンドウズローカルのフォントセットを使わないでくれ。読めないから。
■
いきなり話は変わりますが、きのうの「空耳アワー」でBeach Boysのネタが出た。「Got To Knows The Woman」のサビが「カツ丼 馬ー」に聴こえるっていうの。誰が言ったか知らないが、言われてみれば確かに聴こえる。判定はTシャツゲットでした。
ほかにBeach Boysネタでは「Shut Down」のサビが「シャネラー シャネラー ボディコン 焼酎だー」に聴こえるっていうのが有名。確か年間優秀賞にもノミネートされたんじゃないかな。

■
さらに話は変わりまして、最近入手したアルバムです。George Harrison / The Harri-Spector Show GeorgeとPhil Spectorがスタジオで遊んでいる様子を収録したブート。テープが回っている自覚はあるのかないのか。Wilson Das Neves / samba tropi ブラジル音楽の名ドラマーが60年代末のヒットソングを脳天気にアレンジ。持ってれば笑いは取れそう。ASLN / andante 益子樹さん、益子史枝さんを中心とするウタモノユニット。ミニマルなサウンドとポップなメロディのバランスがいい。鈴木蘭々 / Bottomless Wich 筒美京平ポップスの集大成。売れなかったのが奇跡。avexなんかに移籍して欲しくない。
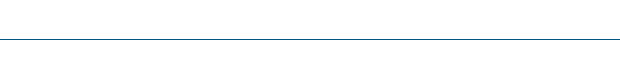
1月22日 寒いならヒーターを買えばいいのに
■
「パンがないのだったらケーキを食べればいいのに」と、マリー・アントワネットは言ったとか言わなかったとか。フランス革命前夜の様子を伝えるエピソードとしてつとに有名な言い回しですが、考えようによっては彼女の発想は斬新にして豪快。そう、お腹がすいたらケーキを食べればいいのです。寒ければヒーターを買えばいいのです。ここに、我々が如何にしてヒーターをゲットするに至ったかを記したいと思います。

■
そもそもバーベキューパーティだというのに午前11時に集合、という時点でイベントの特異性に気づくべきだったかも知れません。参加者はデイジーワールド界隈を徘徊しているネット住人たち。メンバーの一人がお寺のご子息ということで、その境内を拝借しての飲み会だと思っていました。町田駅からタクシーに乗り込み、曲がりくねった道を延々走って辿り着いたのは、丘の上にそびえ立つものすごーく立派なお寺でありました。
■
門構えから漂う風格に圧倒。庭には小川がさらさらと流れています。通された離れには骨董品が無造作に置かれ、その中にひときわ輝くDJセットが。そう、主役はバーベキューなどではなくあくまでレコード。メンバーが持ち回りでお気に入りの曲をかけ、それについて議論するという崇高なレコード鑑賞会なのでした。

■
真っ先に指名された不祥僕、お気楽なパーティミュージックしか持ってこなかったため激しく動揺しましたが、とりあえず場を和ませようと選んだのが坂上弘さんの「交通地獄」。市中のお爺ちゃんが実体験を綴ったラップナンバーで、要は「交通事故で慰謝料をふんだくったにもかかわらずキャバレーで使い果たしてしまった」という実にどうでもいいお話。存在自体が歌謡史上の惨事と言われるナンバーです。これが見事に滑った。二巡目からはGeorge Harrisonのブートやエレクトロニカをかけてなんとか場をつなぎましたが。
■
みなさんの選曲は、戦前ジャズからホーミーからサイン波まで、おおよそ録音文化の辺境を辿る不思議なセットリストでした。「細野晴臣」と「ネット住人」で絞り込み検索をかけると、こんな不思議な時空間がヒットするのだ。なんというかあれだ、若者達の「趣味:音楽鑑賞」にかける熱気に圧倒されました。僕はちゃらんぽらんなリスナーだからね。

■
それにしてもお寺というのは色んな人が出入りするもので、まずやってきたのはネパール出身の生真面目な青年。ネパールのことならなんでも聞いてくださいと言われても咄嗟には質問が出ない。「ネパールと日本の架け橋になりたい」と熱く語る彼に歓迎の舞でも披露してあげたかった。次にやってきたのが、主催者のお兄さんの友達でもうすぐメジャーデビューするというラッパー氏。Hey Yo! 俺のナンバー聴いてくれってノリで入ってきたんだけど、場のムードに戸惑っている風だった。
■
そうそう、ヒーターの話でした。離れがちょっと寒かったのでみんなが車座になってストーブにあたっていたら、ご住職が新品の石油ヒーターを差し入れてくださったの。しかも2台。我々の姿を見て、わざわざ買い出しに行かれたのか。恐るべき寺パワー。恐るべき奉仕の心。そうか、寒い夜はヒーターを買えばいいのです。セーターを買ってる君はまだまだだ。
かくして討論会は深夜にまで及んだのでした。色んな意味で人生の常識を覆す「バーベキューパーティ」だった。最初からこういうもんだとわかってたらちゃんと順応しますんで、みなさんまたひとつよろしく。長文御免。
|