
THE BEACH BOYS
OTHER MEMBERS
MIKE LOVE

ボーカルを担当。
1941年3月15日うまれ。Wilson兄弟のいとこに当たる。根っからのエンタテイナーで、ライブ活動における実質的なリーダー。明るく楽しくわかりやすい音楽を目指し、ステージで盛り上がるヒット曲を熱望したために、アーティスト指向のBrianとはデビュー当時からしばしば衝突していた。
共和党員として政界とコネを持つなど、およそロックアーティストらしからぬエピソードの数々で、一部のファンからはさんざん嫌われてるが、そういう人は彼の愛すべき人間臭さを楽しむ余裕を持ってくれ。Brianのファルセットを下から支え、曲にドライブ感と輝きを与えたのはこの人なのだ。作詞家としても名曲をたくさん残していて、特に「Add Some Music To Your Day」や「Kokomo」のように、キーワードをたたみかけてイメージを構築していくコピーライター的な作風は彼ならではのもの。Paul McCartneyにBeach Boysらしい曲作りのコツを尋ねられ、「地名を入れればいいのさ」と即答したとのエピソードもある。楽器を弾かないので作曲はあんまりしないが、Brianの「芸術作品」にキャッチーなフックをつけるのは得意だったらしく、最大のヒット曲「Good Vibrations」に印象的なバスパートを加えたのは彼だとも言われている。

Almost Summer
Celebration
 1978年5月
1978年5月

自身のバンド、Celebration名義による同名映画のサウンドトラックアルバム。ボーカリストのMikeは出番が少なかったようで、彼が参加しているのはA面だけ。
ペッタリしたリズムで聴いてて楽しくない。と思ったら、Beach Boysの「MIU」や「Light Album」と同時期の作品だそうで、言われてみればあの頃のダメ感、夏を演じることの侘びしさがそこはかとなく漂っている。それでも、Brianと共作したタイトル曲はヒットを記録した (全米28位) 。「It's OK」のセルフカバーは、なぜか別のメンバーがボーカルを担当。Mikeの歌うオリジナルバージョンでは気にならなかったメロディの単調さを露呈してしまい、逆説的にMikeのボーカルの魅力を証明している。

CELEBRATION
Celebration  1979年2月
1979年2月
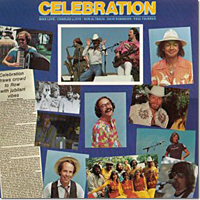
Celebrationとしては唯一のオリジナルアルバム。Mike Loveという人の不可解なところは、ボーカルしか出来ないくせにリードボーカルの座に固執しないで、後ろで変なダンスを踊っているところだ。彼のライブに来るお客さんはたぶん、進まないムーンウォークよりリードボーカルを取る姿を見たいと思う。「MikeはBezとか瀧の元祖ですよ」と評したのは安田理央さん。
このアルバムでもリードボーカルをとっているのは10曲中たった4曲だけ。その代わり、ソングライターとして5曲を提供している。うち1曲は「Gettin' Hungry」のセルフカバー。70年代テイストが加わって別曲のように生まれ変わった。Ron Altbachのキーボードを中心に、Charles Lloydのサックスをフィーチャーしたサウンドは、可もなく不可もなく、手堅くまとまっている。

LOOKING BACK WITH LOVE
 1981年10月
1981年10月

Mike名義でリリースされた唯一のアルバム。いたるところで目の敵にされてるけどそんなに酷いだろうか? 少なくとも同時代のBeach Boysよりはよっぽどましだと思う。
彼のイメージ通り、コーラスを大事にした華やかで明るいアルバム。Beach Boysの「The Beach Boys」や「Still Cruisin'」に通じる、トロピカルなエレポップが聴ける。コーラスアレンジはなんとCurt Boetcher、Beach Boysのハーモニーとはまた違ったセンスで、テンポのいい掛け合いはさすがに楽しい。「Getcha Back」を思わせる暖かい「Looking Back With Love」や、穏やかなデュエットによるオーソドックスなバラード「Paradise Found」はなかなかの名曲だ。浅くて薄いシンセの音に時代を感じてしまうのが残念なところで、Mike自身の不人気もさることながら、オールディーズの名曲を安っぽく解釈する思い入れのなさが評価を下げた原因かも知れない。

A Tribute To Bruce Springsteen Various Artists 2003年5月
Bruce Springsteenのトリビュートアルバムに「Hungry Heart」で参加。コーラスが美しいフォークロック調の演奏。2007年にiTuneのみでシングルカット。

Santa's Goin' To Kokomo Mike Love of The Beach Boys 2006年
iTunesのみで配信されたシングル。Kokomoの名に相応しい穏やかでトロピカルなナンバー。後にクリスマスのコンピレーション「Juvenile Diabetes Research Foundation: More Hope For The Holidays」に収録された。

Juvenile Diabetes Research Foundation: More Hope For The Holidays
Various Artists 2010年
DL販売のみのクリスマスコンピに、前述の「Santa's Goin' To Kokomo」と、Mike Love & Christian Love of the Beach Boys, Fabrice Morvan and the Type 1 Childrens Choir名義の「Closing of the Year」で参加。子供たちのコーラスを中心に添えた厳かなナンバー。また、Bryan Singer, Mike Love, Fabrice Morvan & Doug Clifford名義の「PSA's」にコメントで参加。

(You'll Never Be) Alone On Christmas Mike Love 2015年
原曲は1977年のBeach Boysの幻のクリスマスアルバム用に、Mike LoveとRon Altbachが共作したナンバー。2015年にコメディ映画「A Very Murray Christmas」の挿入歌としてPhoenix feat. Bill Murrayがカバーしたのに併せて、Mikeが新たな歌詞を書き足して配信限定でシングルカットした。


AL JARDINE

ボーカル、リズムギターを担当。
1942年9月3日うまれ。Brianとは高校〜大学を通じての友人で、最初期からバンドに参加していたが、デビュー目前に脱退して歯科医を目指す。しかし、彼の後釜だったDavid Marksがバンドに馴染めなかったため、呼び戻されてサードアルバムから復帰。
フォークソング好きで知られ、古いカバー曲を好んで取りあげた。いかにも人がよさそうで実際いい人らしいが、「Sloop John B」のカバーを提案して大ヒットさせたのに誉められなかったことを今でも根に持っている。作風はキャラクター通り、シンプルでフレンドリー。70年代後半のバンド低迷期に、淀んだ空気を洗うがごとき爽やかな楽曲を提供した。しかし90年代に入ると、メンバーの座を息子に譲って自らは隠居生活に突入する。ええっロックって世襲制だったの? 彼が再び動き始めたのはCarlが亡くなってからのこと。未完成のまま放置されていた幻の名曲「Loop De Loop」を1人で完成させて、これで使命を果したとばかりにBeach Boysとは袂をわかち、自分の息子やBrianの2人の娘たちとAl Jardine, Family & Friendsを結成。やっぱり「家族」というフォーマットにこだわりがあるようだ。現在はAl Jardine and His Endless Summer Band名義で活動。

Papa Loved Mama Al & Matt Jardine 1999年
オリジナルのリリース形態は不明だが、現在は配信のみで入手可能。Garth Brooksのカバー。フィドルとAlのギターのバトルが印象的な力強い演奏。

Live In Las Vegas
 2001年
2001年
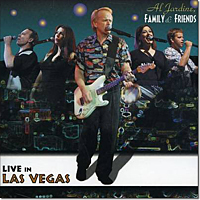
Al Jardine. Family & Friends名義でリリースされたライブアルバム。同時代のMike Love / Bruce Johnstonコンビの「本家」Beach Boysのライブを観たが、比較するのが申し訳ないほどAlのバンドの方が充実している。
セットリストはやはり初期の曲が中心だが、「Pet Sounds」以降の選曲も多く、Las Vegasでのショーとしてはバランスのいい印象。唯一のスタジオテイクは新曲の「California Energy Blues」。タイトル通り、ヘビーなブルーズ調の歌いだしにびっくりするが、すぐにフレンドリーなAlらしいフォークロックに変わる。

Sloop John B: A pirate's Tale 2005年
ASloop John Bをテーマにした絵本。付属CDにシンプルなリメークバージョンを収録。

Christmas Day 2009年
Beach Boysのカバー。配信のみのリリース。ライブ音源。

A Postcard from California
 2010年
2010年
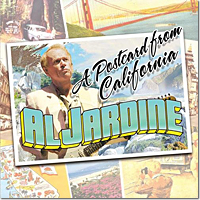
長い時間をかけてレコーディングされた初のオリジナルソロアルバム。ゲストにBrian Wilson、Carl Wilson、Mike Love、Bruce Johnston、David Crosby、Stephen Stills、Neil Young、Steve Miller、Glen Campbellらが参加。なかなか発売元が見つからず、当初は配信とCD-ROMでの販売であった。CD-ROMって...。
4曲のBeach Boysナンバーがあるものの、殆どがAl Jardineによる書きおろし。特にタイトル曲は彼のキャリアの中でもトップクラスの名曲だ。豪華すぎるゲスト陣も主張しすぎず、彼のボーカルとギターの魅力が存分に味わえる。ドライブにぴったりの乾いた風が吹くソフトロックアルバムだ。

Don't Filght The Sea 2011年4月
アルバム「A Postcard from California」からのシングルカット。東日本大震災へのチャリティー商品。B面はBeach Boys名義で「Friends (A Cappella)」。未入手のためいつの音源かは不明。


David Marks

主にギターを担当。
1947年うまれ。Wlison兄弟の近所に住んでいて、Carlのギター友達だった。メジャーデビュー直前、Al Jardineが一時脱退した時に後釜として加入。当時13歳。3rdアルバムからAl Jardineが復帰して4thアルバムのレコーディング中までギター3本体制だったが、やがて居場所を失い脱退。
その後、Wilson兄弟の父親でBeach Boysのマネージャー、Murry WilsonのマネージメントでDavid Marks & The Marksmenを結成、ワーナー・ブラザーズからデビューするもパッとせず。さらにサイケデリックバンドThe Moonにギタリストとして参加、2枚のアルバムをリリースする。Delaney and Bonnie、Warren Zevonなどのセッションに参加した後、バークレーで本格的にギターを学んだ。1971年にBeach Boysへの復帰を打診されるが辞退、Leon RusselやDaniel Mooreなどのセッションに参加した。
1997年、闘病中のCarl Wilsonの代役としてBeach Boysに復帰、バンドであることを辞めてコーラスグループになったBeach Boysの中で、ただひとりギターを演奏した。2012年のアルバム「THAT'S WHY GOD MADE THE RADIO」でもリードギタリストとして活躍。
1992年にソロ・アルバム「Work Tapes」、2003年に「Something Funny Goin' On」、2006年に「I Think About You Often」をリリース。さらにThe Marks-Clifford Bandとして2008年に「Live At The Blue Dolphin '77」、彼の名誉を回復した伝記「The Lost Beach Boy」に合わせて3枚組のレアトラック集「The Lost Years」、The Marksmen時代の音源集「The Ultimate Collectors Edition」をリリースしている。

I Think About You Often
 2006年
2006年
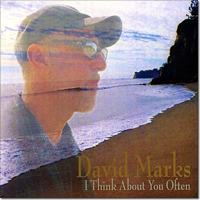
3枚目のソロアルバム。ビーチボーイとして評価されることのなかった彼の実力が伺える、乾いた耳あたりが心地いいフォークロックアルバム。太いエレキギターと繊細なアコースティックギターが作り出す風通しのいいサウンドに暖かいボーカルが揺れる。Mike LoveとBruce Johnstonと3人体制だった90年代末から00年代のBeach Boys、彼がもっと主張していれば「SUMMER IN PARADISE」の失敗を取り返す佳作アルバムができたかも知れない。
ウクレレやマリンバまで飛び出すトロピカルな「Bamboo Shack」、ジャジーな展開にボーカリストとしての魅力が光る「Light of the Spirit」、女性コーラスをバックにソウルフルなギターを弾きまくる「I'm So Clover」、Beach Boysへの愛憎が伺えるブルース「I Ain't Goin' Surfin'」あたりが聴きもの。


BLONDIE CHAPLIN

主にギターとベースを担当。
1951年7月7日、南アフリカうまれ。Ricky FataarらとソウルバンドThe Flamesを結成して1965年にレコードデビュー。Jerry Butlerのカバー「For Your Precious Love」が、アパルトヘイト政策下の南アフリカで黒人バンドとしては初めてのNo.1ヒットを記録した。勢いにのってロンドンに進出したところ、ヨーロッパツアー中のCarl Wilsonに見い出されて、70年にはCarlのプロデュースでアルバム「The Flame」を制作。しかし、その直後にバンドは敢え無く解散してしまう。
一度は国に戻ったものの、Carlの計らいでRickyと共に71年にBeach Boysに加入。作風はいかにもCarlが好きそうなソウルフルなポップスで、力強い演奏やファンキーなボーカルと相まってバンドのカラーを大きく広げた。特にライブアルバム「In Concert」のどっしりしたリズムは、明らかにBlondieとRickyの功績。しかしやっぱり芸風が合わず、マネージャーとの確執の末73年には脱退した。

脱退後のBlondieは解散前後のThe Bandと交流を持ち、各メンバーのソロプロジェクトに参加。96年の再結成アルバム「High On The Hog」でも数曲でギターを演奏し、渋いバラード曲「Where I Should Always Be」を提供している。また、Rickyが参加していたThe Bump Bandをサポート、小原礼との親交を深めてアルバム「ピカレスク」の全曲を共作し、リードボーカルを担当した。さらにセッションミュージシャンとしてThe Byrds、Paul Betterfield、Bonnie Raitt、Mick Taylorらのアルバムにも参加している。
97年にはRolling Stonesのアルバム「Bridges To Babylon」に参加、ほぼ全曲でバックボーカルとパーカッションを担当しているほか、数曲でベースとピアノを演奏した。ワールドツアーにも同行して、時にはギターを演奏するシーンも見られたとか。Stones史上、メンバー以外の人間がステージでギターを弾くのは初めてのことだそう。続くアルバム「A Bigger Bang」にも参加。ツアーにも同行している。その様子はライブアルバム「No Security」「Shine A Light」で聴くことができる。
2015年にはBrian Wilsonのソロアルバム「No Pier Pressure」に参加して、久しぶりに旧交を温めた。また相方のRickyも、アルバムのリリース記念ライブに参加。この2人が2012年のBeach Boys一時再結成に参加していれば!! Mikeとそりが合わなかったのかも知れない。

Burning Soul! / Soulfire!!
The Flames
 2010年
2010年

1967年リリースの2nd「Burning Soul!」と1968年リリースの3rd「Soulfire!!」をカップリングしたCD。アパルトヘイト政策下の南アフリカで黒人バンドとして初めてNo.1ヒットを記録した、「For Your Precious Love」を聴くことができる。楽曲は殆ど当時のソウルナンバーのカバー。演奏は可もなく不可もなく。
同時期に1st「Ummm! Ummm! Oh Yeah!!!」と「That's Enough (詳細不明) 」にシングル曲を併せたCDがリリースされている (未聴) 。

The Flame
The Flames
 1970年
1970年

ものの本にはFlames唯一のアルバムと書かれているがとんでもない、10代半ばからレコーディング活動を始めた彼ら、これが5枚目のオリジナルアルバムにあたる。
南アフリカのソウルというとコテコテのブラックミュージックを想像してしまうが、手触りはイギリスのモッズバンドに近い。アフリカからアメリカに渡ったリズムがソウルミュージックに結実し、それに憧れたヨーロッパの若者たちのサウンドを楽しむアフリカの少年たち(つまり地球をひと回り)。ファンキーなのに軽くて非常に聴きやすい。アップテンポなナンバーはSmall Faces系だが、スローになるとBeatles風のコーラスがついてGeorge Harrisonっぽくなる。Blondieのソロほどキャッチーさはないが、バンドらしいまとまりのある演奏で、妙に力が入り過ぎてるところも含めて微笑ましい仕上がり。レコードではこんなもんだがライブはきっと楽しかっただろう。このアルバムを聴いていると、輝く未来が約束されていたはずの彼らを引き抜いたのが、よりによってBrother Labelだったことは、彼らにとって本当に幸せだったのかと心配になってくる。
ところでこのLPには、Brother Label自慢のクアドロフォニックシステムがどうのこうのいうイラスト入りのペラ紙が同封されていた。

Blondie Chaplin
 1977年
1977年
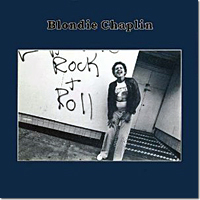
キャッチーなコンポーザーとしての魅力がつまったソロアルバム。ブラックミュージックへの愛情にブリティッシュロックのフィルターを通して、フレンドリーなポップスに昇華している。いい意味でのうさん臭さ、偽物感を感じさせる作風はCarl譲りだ。たたみかけるようなリフレインが印象的な「Bye Bye Babe」や「Gimme More Rock N' Roll」あたり。でも演奏はCarlのソロよりずっと締まっていてかっこいい。
プロデュースは、Bob DylanやThe Band、Eric Claptonのアルバムで知られるRod Fraboni。ドラムスはもちろんRickyで、ほかにもLittle Featのメンバーをはじめ豪華な顔ぶれが揃っている。つくづく大物に縁があるが、当人には大仰なイメージが全くないのがいい。ベストトラックは「Riverboat Queen」だろうか。Garth Hudsonのアコーディオンがフィーっと流れてくるだけでもう降参だ。肝心のボーカルはファンキーでかっこいいのだが、いまいち抜けが悪いというか、押せ押せで一本調子に聴こえてしまうのが残念。ところで「Say You Need Me」のサビがどうしても「What's Going Onナリ」に聴こえるのは僕だけか。コロ助? どうでもいい話だった。申し訳ない。

Between Us
 2006年
2006年
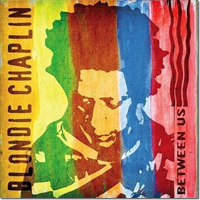
Keith RichardsやRonnie Wood、Bob Dylanとの仕事でも知られる同郷のKeith Lentinを共同プロデューサーに立てた、久しぶりのソロアルバム。Blondieのボーカル・ギター・パーカッション、Keithのベース、Anton Figのドラムスを中心にした、シンプルで風通しのいい演奏。ギターも主張しすぎず、ソングライター・ボーカリストとしてのBlondieの魅力が詰まっている。
ソングライティングにアメリカンルーツミュージックの影響が感じられるのは、彼のBB以降のキャリアゆえか。胡散臭さも消えて自分のものにしている。ボーカルはさすがに以前の押せ押せではなく一歩引いたスタイルで、涼やかに表情豊かになっている。


RICKY FATAAR

主にドラムスを担当。
1952年5月9日、南アフリカうまれ。The Flamesとして活動した後、71年にDennisの代役としてBeach Boysに加入。Blondieとの共作で数々の名曲を提供し、骨のあるリズムでBeach Boysにライブバンドとしての名声をもたらした。しかし彼もバンドのカラーに馴染めず、Blondie脱退の翌年74年には脱退。
脱退後は、元Small FacesのIan McLagan、元Sadistic Mika Bandの小原礼、ギタリストのJohnny Lee SchellとThe Bump Bandを結成、Ian McLagan & The Bump Band名義でアルバム「Bump in the Night」を発表した(現在活動中のBump Bandはほぼ別物)。また、セッションミュージシャンとしてBonnie Raitt、Barry Mann、David Crosby、Roy Orbison、Crowded Houseらのレコーディングに参加。プロデュース活動も盛んで、Boz Scaggsの復活アルバムは彼の仕事。現在はオーストラリアに移住して、現地でコメディ映画の音楽を多数手掛けている。このうち少なくとも「Spotswood」「Les Patterson Saves The World」の2作品についてはサントラ盤が出ている。
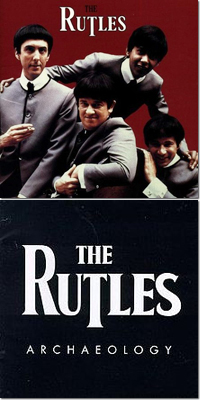
神出鬼没のRickyだが、よく知られているのはやっぱりThe Rutlesとしての活動だろう。Rutlesは、Monty Python出身のコメディアンEric Idleや、Bonzo Dog Doo Dah BandのNeil Innesらと結成したBeatlesのパロディバンド。76年に、サタデー・ナイト・ライブのスタッフと共同で、Beatlesの歴史を徹底的におちょくった偽ドキュメント番組「All You Need Is Cash」を制作して大きな話題を呼んだ。
番組のサウンドトラックとして発表された「The Rutles」はロック史上の怪作。オマージュなんて上等なもんでなく、これぞパロディ。よく聴けばエフェクターの使い方とかパーカッションとか緩いんだが、そんなことはもうどうでもいいんだ、笑えれば。でたらめなライナーノートも最高で、こういうセンスはBeach Boysからは到底でてこない。Rickyはこのアルバムでドラムス・ボーカル・ギター・シタールを担当した(番組での彼の役どころはGeorge Harrisonだった)。
そのまま伝説の座に納まっていればよかったものを、96年にはBeatlesの「Anthology」シリーズのヒットを受けて復活、アルバム「Archaeology」を発表した。コンセプトメーカーのEric Idleが参加を拒否したためバカバカしさは半減だが、そのかわり演奏のクオリティは著しく向上。パロディも合わせ技が増えて、もはやOasisとたいして変わらなくなってしまった。しっかりしたリズムと重厚なオーケストラのサウンドは前作以上にBeatles的、ある意味でブリティッシュロックの傑作だ。気を抜いて聴いているとうっかり感動してしまう。
|