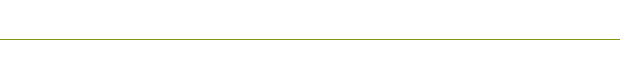
FUJI ROCK FESTIVAL '02 7.27

■
2日目の朝。高原の風を部屋に入れて途中参加する仲間を待つ。この日の一発目はGreen StageにてLove Psychedelico。冷やかしで見てたんだが、馬鹿にしたもんではない。やたら低いベースを中心に、バックバンドが締まった演奏をみせる。本人達もかなりの自信家らしくて、「Like A Rolling Stone」のカバーも様になっていた。しかしその「そつのなさ」からどう抜け出すのかが課題になりそう。
ひとつ、MCが英語なのは嫌味ったらしかった。僕は外タレが「ドモアリガト」というのを法律で禁じて頂きたいという思想の持ち主だが、それと同じくらいデリコの「Thank You」を禁止したい。もうひとつ、ギター氏がMike Myersにそっくりだった。。

■
木陰でまったりお喋りした後、Red MarqueeでBuffalo Daughterを見る。彼らのことをスタジオ実験バンドだと思っていたんだがそれは間違い。素晴らしいライブバンドだ。たった4人で繰り出す音は鮮やかでアイデアに溢れ、しかし徹底的に無駄を省いてリズムの核を浮き上がらせる。研ぎ澄まされたサウンドの隙き間からこぼれ出るほのかな暖かさは、ゴムのようなベースラインのせいなのか、ムーグの音色のせいなのか、男女混成バンドの微妙な構図によるものなのか。映像もトランス的な演出だったのだが、モチーフに歩く人やダンサーのシルエットが組み込まれ、オーガニックな印象を残した。
MCでは不気味なエピソードを披露。開演前、少年ナイフのメンバーが楽屋に来てくれたのだが、「テニスコートの予約を入れてますんで、じゃっ」と言って帰ってしまったという。テニスウェアの少年ナイフ。見たくねえ!

■
Buffalo Daughterの静かな熱を胸に残したまま、Green Stageに戻って忌野清志郎&矢野顕子を見る。忌野はFUJI ROCKに出過ぎである。今年はスペシャルユニットで2ステージをこなす。矢野はいつものようにピアノの前に座り、忌野はギターとサックスを持ち替えながら歌う。ゆったりとしたいい空気が流れていた。「海辺のワインディングロード」「多摩蘭坂」。名曲の数々が、Buffalo Daughterの興奮をチルアウトしてくれた。
最後は矢野顕子が生んだ世界屈指のピュアラブソング「ひとつだけ」。これを忌野が歌うと、そっくりそのまま男の子の歌になる。「悲しい気分の時も、僕のことを忘れないでいておくれよ」。最高の「ひとつだけ」。

■
さて、ついに今年のFUJI ROCKで最大の波紋を呼んだあの男がステージに立つ。井上陽水である。夢の中へである。ホテルはリバーサイドである。氷の世界である。なぜに彼がFUJI ROCKに呼ばれたのか。みんな遠巻きに怪訝な目でステージを見つめた。
奇妙な静まりの中で、アコギを抱えた彼はこう歌った。「都会では自殺する若者が増えている」。日射しいっぱいの森の中で。ブレイクのあと一転、ガツンとヘビーなバンドが入る。その瞬間、両腕を振り上げた若者たちがシートを蹴散らしてステージに殺到した!圧倒的な演奏力、そしてボーカルの説得力。シュールな歌詞を綴るフォークシンガーがロックアーティストになった瞬間だ。それはBob DylanのRoyal Albert Hallだった。

■
ディストーションギターがうなる「アジアの純真」からジャジーな「飾りじゃないのよ涙は」、ハードな打ち込みモノに変貌した「氷の世界」、そしてやっぱり「少年時代」。遠い夏への憧れを歌ったこの歌が、トンボ舞う夕暮れの森にこだますると、鼻ピアスの少年やピンクの髪の少女がポロポロと涙を流し、抱き合って声を合わせた。本当に、そうだった。
普段は洋楽を聴いて、カリフォルニアやリヴァプールに憧れていても、やっぱりジャパンに生まれ、陽水を聴いて育ってしまった事実にはあがなえない。カキ氷と蚊取り線香の世界を、僕たちはもう一度見直す必要がある。登場の一瞬に込められた意外性、聴き手をドキッとさせる緊迫感。これこそロックだと思う。あの日あの時の陽水は自宅のスピーカーからは聴こえてこない。苗場の森のマジックだった。

■
遥か遠くにPet Shop Boysを聴き流しながら陽水の余韻に浸る。さてSonic Youthを見に行こうと思ったら、奇妙にアレンジされた「Tomorrow Never Knows」に耳を奪われた。Chemical Brothers登場。4つ打ちの狂騒である。
サンプラーにしこまれたフレーズの数々とキーボード、VJとシンクロした照明。つまりはスイッチのON / OFFだけで人をここまで狂わせてしまうのはなぜか。彼らのスイッチングはヴァイブレイターに似ている(使ったことはないが)。つまり、じらしのテクニックなのだ。

■
スネアのフレーズを延々繰り替えし、ここでバスドラが欲しい〜!という状態を16小節くらい引っ張って、欲求を極限まで高めた状態でバスドラを入れる。ここでエクスタシーを向かえるのだ。しかし、トランス状態に入りそうなところでブレーク、静かなキーボードのリフに戻ったり。ひたすらその繰り返しだった。すごくエッチ。ジャズ好きがテクノに走りがちなのは、そういうSM的な快楽に合い通じるものがあるんだと思う。最後は「Love Is All」のメッセージ。Beatlesネタのサンドイッチでわかりやすく締めた。
帰りの道すがら、線香花火を囲んで語りあった。いま思えば陽水の罠だったのか。なんとなく「少年時代」、であった。3日目に続く。
|