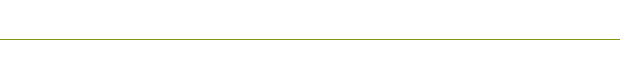
FUJI ROCK FESTIVAL '02 7.26

■
去年のFUJI ROCKから帰ってきて僕は呆然としていた。音楽と森のこと。恍惚と浄化のこと。少年と少女のこと。ケイオスとコスモスのこと。音とはたかが空気の振動で、でもそのヴァイブレーションがこんなにも人を動かしてしまうという事実について。だから今年も行くのです。祝祭の場に。音楽の原点に。ロックを浴びて今日を生き抜くために。
越後湯沢駅に降り立つとさわやかな高原の空気。と言いたいところだが日射しがあちい。シャトルバスに乗り込み苗場の森を目指す。各国から集まってきたロックファンの弾ける笑顔に囲まれて、テンションもあがってきた。気がついたら入場前に500ml缶が3本カラになっていた。

■
最初のお目当ては東京スカパラダイスオーケストラ。3年前におきた青木達之の悲しい死亡事故。また、同じく悲しい出来事によって一人きりのfishmansになってしまった茂木欣一。茂木が青木の代打を務め、スカパラに正式メンバーとして迎え入れられたことは日本のロック史の美談だが、果たして音楽的にはどうなのか? 結果はばっちり。茂木は自分のスタイルを変えることなく、見事にスカパラの一員になっていた。どことなく顔つきもスカパラっぽい男臭さを醸し出していた。
徹底的にスカのリズムを貫くパフォーマンスは単調になりがちだが、彼らはライブバンドとしての見せ方を知ってる。右に左に振り回されるトロンボーンの迫力にこっちの腰も揺れる。肩車されたちっちゃな男の子が拳を振り上げる姿がたまらなく可愛いかった。生理レベルで誰でもウェルカムなエンターテイメント精神。長い長いソロのあと、一気にサビのフレーズが弾けた瞬間、雲間から太陽の光が降り注いだ! 偶然をも味方にしてしまう迫力のステージだった。

■
空き時間にWhite Stageに向かいFidel Nadelを見る。どこの誰だか全然知らない。レゲエのリズムにスキャットマン・ジョンみたいな早口のボーカルが乗る。観客をアジってるのだが、魔法使いみたいな衣装とココリコ田中みたいな動きに笑ってしまった。コード進行がKnockin' On Heaven's DoorだったりA Whiter Shade of Paleだったりするのはご愛嬌。楽しかったです。
White Stageに行ったらやっぱり木陰の清流に足を浸さなくては。死ぬほど冷たい水が焼けた肌にしみこむ。目の前では女の子たちが水鉄砲で遊んでいる。なんて素敵な光景。君たちこけたら心臓発作で死ぬぞ。

■
Green Stageに戻って木陰でケバブを食す。吹き抜ける風が気持ちいい。
続いてV∞REDOMSを。向かい合わせにセッティングされた3台のドラムセットとサンプラー。お互いの顔を見合わせて、探りあいのインプロビゼーションが始まった。ばらばらだった4人のリズムが一つのグルーヴにまとまり、やがてポリリズムの洪水に。EYヨのトリッキーなDJとボイスパフォーマンスが呪術的な空間を生み出す。音響の快楽を突き詰めると原始に帰っていくのだろうか。
しかし彼らはトランス状態に突入する寸前でリズムを崩し、聴き手の予想を裏切り続けるのだった。お互いの目を見据える緊張感を維持し続け、いいプレイが飛び出したとたんに笑顔がこぼれる。ライブパフォーマンスの醍醐味。Yoshimiの汗がたまらなく美しかった。
続いてRed MarqueeにてTelevisionを見る。まさにMarquee Moonって感じか。うーん、これが賛否両論。V∞REDOMSの後では懐メロバンドにしか見えなかったな。彼らのスタイルはずいぶん真似されちゃったし。「See No Evil」で延々引っ張るのは如何なものか。

■
再びWhite Stageに登ってManu Chao Radio Bemba Sound Systemを見る。Mano Negraのリーダーの新プロジェクトだそう。これが大ヒット! 基本はポルカだと思うんだが、いきなりスカになったりレゲエになったりして最後は8ビートに突入。敬礼や駆け足のユーモラスな動きから、典型的なロックスタイルを揶揄するようなポーズまで、キビキビしていて実に気持ちいい。いつのまにか前に出て一緒に踊ってしまった。
ドラムの抜けのよさ、ギター・ベースの締まりのよさ、アコーディオンの柔らかさ、チープなキーボードの脱力感まで含めて非常にバランスがいい。スタイルは超バカだが、おそろしく知的に計算されてる。資料によると、かなり政治色の強いスタンスを打ち出しているようだが、それを狂騒のリズムにくるんでしまうところにフランス人のエスプリを見た。長渕剛とかに聴かせてやりたいぜ。

■
締めはFunkadelicにするかPatti Smithにするか迷ったが、去年のベストアクトだったPattiを選ぶ。去年Neil Youngが使ったロウソクのセットを譲り受け、Field Of Heavenらしい幻想的な舞台。1曲目から機材のトラブルが続き、出音にも納得がいかない様子。ステージ上に緊張感が走る。急に挑発的になったり、かと思うと手を振って愛嬌をふりまいたり。「今朝は6時に起きて森の中を散歩したの。今夜が素敵な夜になるとわかったわ。ここは本当にヘヴンね。」などと普通っぽいことを言う。本当は怒っていたのか楽しんでいたのか。最後までわからなかった。豹変する彼女の態度にただ翻弄されていた。
ただ確かなことは、いくら中指を突き立てようと、つばをはこうと、客に背を向けようと、ギターの弦を切ろうと、彼女には持って生まれた気品があり、洗練された説得力があるということだ。彼女の全盛期からはずいぶん時間がたち、社会も変化していったが、往年の名曲は今の僕たちにも拳に力を込めさせる気迫がある。結局僕は彼女に惑わされ、踊らされていた。2日目に続く。
|