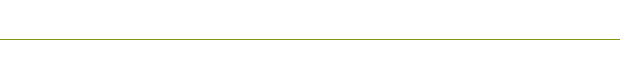
FUJI ROCK FESTIVAL '04 7.30

■
あれは去年のFUJI ROCK、明けきれぬ梅雨にさんざん苦しめられたにも関わらず、なんで今年もチケットを取ってしまったのか。それはおそらく音楽が自然の中で生まれたからであり、ミトコンドリアイヴが木々に囲まれて生まれたからであり、都会の片隅でのうのうと生きている僕らにはコスモスとケイオスのバランスを矯正する必要があるからではなかろうか。
今年は梅雨こそ開けたものの、迷走し停滞する台風に悩まされた。新幹線を降り立った越後湯沢駅は快晴、苗場の空も晴れていると聞いてまずは一安心。バス乗り込み会場へと向かう。

■
去年は1時間半並んだシャトルバスが、今年はガラガラであった。程よい陽射しの中、美味しいソフトクリームを食べる。完璧すぎる滑り出し。苗場の空は、晴れていると言えば晴れていた。しかし強風にあおられ、目の高さの雲が左から右へと猛スピードで流れて行く。その度に霧になり小雨になり、また嘘のように青空になる。
まずはメインステージのGreen Stageにシートを広げ、本拠地を作った。折しもPe'zが演奏中。ホーン中心の日本のインストバンド。オールドタイミーなフレーズも飛び出して、和やかでお茶目な演奏を繰り広げる。ライブ中心で人気を広げてきたバンドだそうだけど、ラウンジイベントなんかでも使えそうな感じだ。ただ、お約束のソロ回しとかしちゃうあたりはやっぱりテクニック至上主義から抜けきれていないのかな。キーボードソロが意外な見せ場ではあったが。

■
露店街Oasisでモチ豚丼を食べたあと、またもGreen StageでThe Blind Boys Of Alabamaを見る。出てきたのは、いったいいつの時代のボーイズかってくらいよぼよぼのお爺さん達。後で資料を見ると1939年結成とある。そしておそらく何人かはBlindだと思われ、比較的若いギター氏の肩を借りながら、色んな意味で足下がおぼつかない様子で登場。ときどき椅子から3秒くらい立ち上がっただけで拍手が起きる。
曲は典型的なブルーズ・ゴスペルスタイルで、6人編成中4人が楽器を演奏、そして全員でボーカルを取る。ルーズなイントロから自然に曲が始まり、気負いのない演奏で南部の風景を描き出す。すごい爺さんがかっこいいゴスペルをやる、それだけで全てオーケーだ。演奏力も然ることながら、壮絶な肺活量で唸るコブシが見せ所。最後は客席に降りて、熱い声援を送る観客ひとりひとりに握手するサービス。Blindな彼らに感動を伝えるには、声援を送るか彼らの手を握りしめるしかない。

■
続いてライブハウスのRed MarqueeでAsian Kung-Fu Generationを見る。去年のFUJI ROCKでは無料スペースのRookie A Go Goに出演していた彼ら、今年は一気に5000人収容のRed Marqueeに出演とは大出世だ。「盛り上がってます?...空気読めなくてすいません...朝から会場を見て回っていたら...赤犬というバンドのボーカルがキンタマ出してて...なんだか妙にテンションがあがっております」なんて初々しいMCを挟んで怒濤のヒット曲攻勢へ。単調なリズムを刻んでいるようでいて、巧みにテンポを変えて緩急をつけるテクニシャンだった。
ただ客層がロックの客じゃなくてJ-POPの客なんだよねー。彼らがそういうフィールドで満足しているならいいけれど、もっと耳の肥えた観客を楽しませることが出来るバンドだと思うのでちょっと残念。

■
Green Stageに戻って、1日限りの奇跡の復活、ザ・ルースターズを見る。ボーカル大江慎也のかくも長き療養生活、花田裕之や井上富雄の若手バンドとの交流で、ともすれば神格化されつつある彼らの存在。実際に見てみるとまあ伝説ってこんなもんだろうな、というステージ。ロックというより50's〜60'sのブルースルーツの「ロックンロール」を思わせる楽曲が続く。
大江慎也のボーカルは、ロック的に見れば危険なムード、音楽的に見ればあぶなっかしくて、そのことが観客の緊張感を維持していた。後半になると池畑潤二のドラムが和太鼓のように暴れ回り、80'sバンドらしいポップな一面や、スカを取り入れたリズムで観客を沸かせる。おそらく現役時代から彼らの復活を待ち望んでいたオールドファンにはたまらないステージだっただろう。思い入れのない僕も「C.M.C.」が始まった時には興奮した。

■
次に何を見ようか迷ったのだが、川のほとりのWhite Stageまで足を運び、Ozomatliを見る。これが大ヒット。レゲエを中心に、アフリカンやヒップホップ、ポルカに音頭と、世界中のダンスミュージックをミクスチャーして、バカバカしくも真摯なメッセージで包む。政治的な言葉を発しているのに小難しくならず、とりあえず踊っちゃえというスタンスは、Manu Chaoに近いのかな。メインMCはスーパーマンのTシャツ着てるし。もうどうでもいいんだよそんなことは。僕らも心にスーパーマンのTシャツを着て、バカのように踊り狂った。
最後はメンバー全員が客席に降りてきて、観客の中を練り歩きながら阿波踊りのようなリズムで盛り上げる。誰が吹き込んだのか知らないが、「カラスの勝手でしょ」のコール&レスポンスを繰り返して去って行った。音楽が国境を超えるというのはこういうことを言うのだ。あまりにも楽しくて楽しくて、なぜか泣きそうになった!

■
ふたたびGreen Stageに戻って、この日のお目当てのひとつ、Pixiesを見る。これまた奇跡の復活組、感慨ひとしお。NirvanaやFlaming Lipsに強く影響を与えたというそのサウンドは、今もなお有効だった。ソリッドな切れ味のあるドラムスと女性ならではのしなやかさを持つベース、その抑制されたリズム隊の上を唐突に暴れ回るギター、あの太い体から繰り出されるメロディアスで表情豊かなボーカル。BlackとKimの男女のハーモニーも、もちろんばっちり。時に16ビートを打ち砕く意表をついたブレイク、変拍子のアクセントにはハッとさせられっぱなしで、つまりは全てが正しくPixiesであった。そしてその正しいPixiesサウンドが、今の観客に素直に受け入れられているのも嬉しい事実だし、彼ら自身がほんとに演奏を楽しんでた。

■
ラストはもちろんLou Reed。Pixiesとは比較にならないくらい地味なステージ。でも集中して聴けば、緩急飽きさせない演奏になっている。ワイルドな彼のイメージからは想像もつかない繊細なギターソロ、時にエキセントリックなチェロソロ、そしてコーラスワークの妙、テンポチェンジの妙。選曲も最近の曲が中心で、往年のヒット曲にコブシを挙げてオーって感じではない。勢いで押してしまうのではなく、今の彼が表現したいことを丁寧に紡いでいく感じ。観客の空気はともかく、ギターを弾く当人は実に楽しそうだった。
アンコールではポエトリーリーディングを披露。しかし自身をオリジナルラッパーと表現する彼のこと、極めてラップよりのパフォーマンスであった。そして最後は「Sweet Jane」に「Perfect Day」。最後にぽつりと「ドゥモアリゲトゥ」。それは、洋楽をそれなりに聴いてきた僕の中でも一番発音の悪い「どうもありがとう」であった。2日目に続く。
|